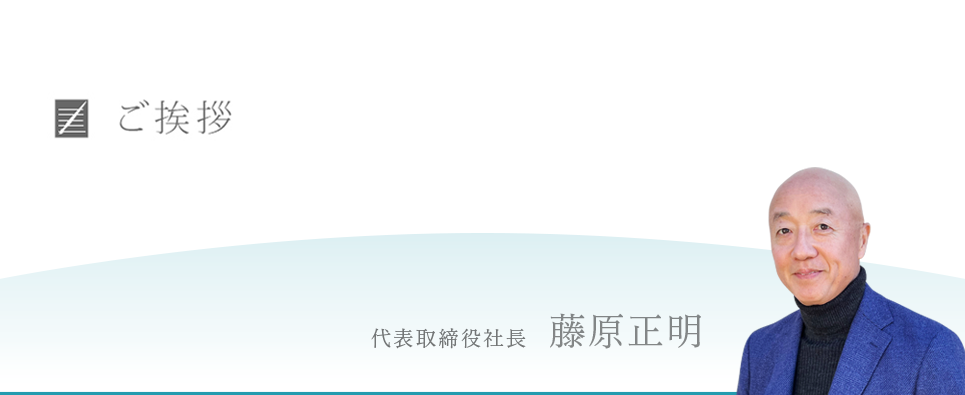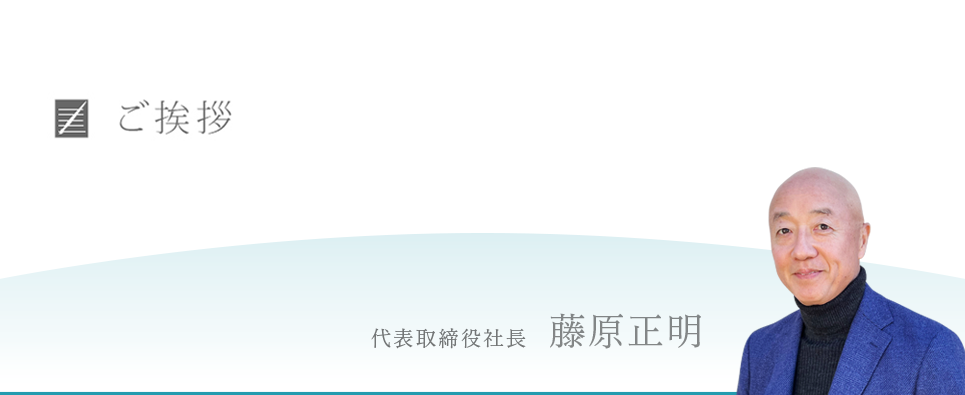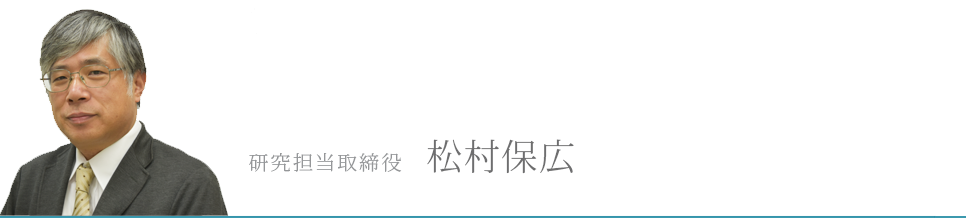ご挨拶
2024年6月30日付で当社代表取締役社長に就任致しました藤原正明です。いよいよ世界に羽ばたくべく本格的な助走のタイミングで前任の吉松賢太郎からバトンを引き継ぎました。未来の医療に革新をもたらす可能性に満ちたパイプラインを複数保有する状況まで導いてきた経験豊かな仲間達と一緒に全力で走れることを嬉しく思いつつ、不確実性に満ちた今後の道程において、リーダーを仰せつかった事実に身が引き締まる思いです。
株式会社凜研究所は、2016年1月に設立された国立がん研究センター発の認定ベンチャーです。同センター発ベンチャーの中では唯一抗体医薬による事業化を目指しています。がん治療用の抗体医薬も多数が臨床で利用可能となっており、多くのがんは既に不治の病ではありません。ただ、全世界的に高齢化が進む中で老化に伴いがん発症率は今後も上昇することは疑う余地もなく、2人に1人が生涯に一度は経験する疾患となっています。その中で注目すべきは既存の治療法では救うことが出来ないがん患者さんが未だに多く存在する現実です。
我々が研究開発を進めている抗がんパイプラインは、既存薬物に耐性を獲得したがん、すい臓がん、小児にも多く発症する脳腫瘍などに効果を示す可能性が示唆されています。これらのパイプラインについて臨床試験で安全性と効果を証明し、製薬メーカーなどへのライセンスによりグローバルでの開発、販売を可能にすることで、新たな治療を待ち望む多くの患者様の切実な想いをかなえることこそが、我々に課された社会的な使命と考えています。
こうしたユニークなパイプラインを生み出した国立がん研究センターの分野長であった松村保広は、元来、薬をがんのところに選択的に届け、抗がん効果が高く、全身の体には優しいDDS(Drug Delivery System)の開発に取り組んできました。がん治療におけるDDSの理論的支柱となったEnhanced Permeability and Retention (EPR)効果(がん周囲の血管では透過性が亢進し、抗体のような高分子でも局所に漏出し留まる現象)を1986年に前田教授とともに発表し、EPR効果はマウス実験のレベルでは世界的に受け入れられました。一方「臨床のがんでは十分な機能が果たせていない」理由を長年探求してきました。その結果、
1) 悪性度の高いがんでは、血管浸潤・破壊等による血液凝固亢進の結果、不溶性フィブリン(insoluble fibrin :IF)やコラーゲン沈着等によりがん間質が形成される。
2) 抗体医薬を含む高分子製剤はEPR効果でがん組織に集積してもがん間質バリアによりがんでの均一な分布が妨げられる。
といった問題点を明らかにしました。この固形がん特有の問題克服のためがん間質ターゲティングCancer Stromal Targeting (CAST)療法を提唱しました。
CAST療法として開発する製剤の要件は
1) ヒト化抗IF特異抗体は前駆体のfibrinogenやIF分解産物と結合しない。
2) Antibody drug conjugate (ADC)はがん間質中のIFと、特異的に結合した時のみ抗がん剤MMAEを遊離する。
3) 抗体エピトープはIF形成時のみに出現し、マウス、サル、ヒトまで一致し、動物実験データがヒトに外挿可能。
4) IF陽性の膠芽腫、膵がんPDXに対して著明な抗腫瘍効果を確認。
5)血栓マウスモデルにADCを投与しても、血栓部位での出血や組織障害を認めない。
これらの特徴を満たすことにより、ADCは血中のfibrinogenで中和されず、がん部のIFに到達し、IF上でのみMMAEリリースがおき、がん以外での抗がん剤の影響は最小限となります。通常のADCと異なり、標的分子はがん細胞表面分子ではなく、がんのheterogeneity(固有の異質性)の影響はなく、正常上皮系幹細胞への結合が無いため、間質性肺炎や下痢等が起こりにくいと予想されます。
次に、松村は、ほとんどのADCの標的分子が、がん細胞だけでなく、正常の上皮においても高発現しており、皮膚湿疹、潰瘍、肝障害、下痢などが起きることを問題視し、より、がん特異分子を見出すために、内視鏡検査後の大腸内腔洗浄液から分離した正常大腸上皮細胞と大腸がん細胞との間で遺伝子の網羅的発現解析を行い、新しい大腸がんに特異的に発現する分子を数種特定しました。その内の1つがTMEM180であり、後述のヒト化抗TMEM180抗体の発明に繋がった訳です。
同手法は、乳がんや膵がんなど他の難治性がんの新規抗原探索にも応用可能であることから、新たなパイプラインの継続的な創出を実現してまいります。
当社のパイプラインの中で先頭を走っているヒト化抗TMEM180抗体は、2023年1月に臨床試験が開始されました。TMEM180は正常組織では殆ど発現されていないことは確認済でしたが、フェーズ1の用量漸増コホートにおいて、これまでの投与量では想定通り極めて安全であることが確認されています。今後の試験の進捗において明確な効果発現が待たれます。
2番目のパイプラインは、先述の不溶性フィブリンに特異的に反応し、血中の可溶性フィブリンやフィブリノーゲンには反応しないヒト化抗不溶性フィブリン抗体に薬物を結合させたAntibody Drug Conjugate(ADC)です。昨今ADCががん医理療の現場で強い効果を示すことが確認され、世界的にその注目度が急上昇しています。当社のADCは不溶性フィブリンが多く集積している間質でのみ抗体と抗がん剤を繋ぐリンカーが切れるように設計されており、動物実験では効果と同時により高い安全性を示す可能性が確認されています。2026年の臨床試験開始を目指して開発を進めています。
これらの成果は、松村ががんの攻略において、本質的な課題1つ1つに向き合い、仮説の検証を重ねて乗り越えた結果に基づきます。結果的に現行治療では難攻不落の難治性がん攻略に向けての期待が膨らみます。
こうした背景を踏まえて、2023年から本格的なライセンスや共同研究に向けての活動を開始したことにより、これらのパイプラインは海外の製薬企業やベンチャー企業において注目を集め始めております。
スタートアップにとって事業化に向けた活動が重要なのは言うまでもありませんが、我々が大事だと考えているのは、様々なステークホルダーの皆様との協業です。これまでも国立がん研究センターとの共同研究、政府からの助成事業への採択などのご支援によって、ここまで辿り着くことが出来ました。「難治性のがん患者さんに新たな治療をお届けしたい!」と言う我々の思いを1日も早く高いレベルで実現させる為に、これまで以上に皆様との協業が重要と考えておりますので、倍旧のご支援・ご鞭撻を賜れば何よりです。何卒宜しくお願いいたします。